こんにちは!
講師のむらかみです。
私のピアノの発表会の準備は、演奏のマナー、聴く側のマナーまでお話しし、演奏前の礼に至っては1ヶ月以上前から何度も練習をします。
それは、音楽を学ぶ上で「マナー」というものがとても大切だと思うからです。
今日は、そんなお話しをしていきたいと思います。
子供教育のヒントになれば幸いです。
ピンポ〜ンのお返事
レッスンにお越しいただく時、チャイムを鳴らしていただいています。
そして、インターフォン越しに「は〜い、どうぞ〜」と私が言うのですが、ちゃんと入って来られているか少し確認してからインターフォンの通話を切っています。
もう、何年も昔のことですが、1人だけ、いつも違和感を感じる子がいました。
どうして気になってしまうのか?
深掘りして、考えたことがありました。
大抵の子はチャイムを鳴らした後、私の「は〜い、どうぞ〜」の声を待って、ガチャリとドアを開けます。
「おじゃましま〜す」という子もいるし、「こんにちは〜」という子もいるし、「よろしくお願いしま〜す」と大きな声で言いながら入ってきてくれる子もいます。
中には、何も言わないけれどドアを開けることが「理解した」というお返事のように見える子もいました。こういった子の場合も特に違和感を感じることはないのです。
違和感を感じるその子は、「は〜い、どうぞ〜」のあと、お母さんがいる、後ろを振り返りながらドアを開けては閉めたり、毎回前を向かず、後ろを見ているのです。まるで、私の「は〜い、どうぞ〜」が聞こえていないかのようなそぶりです。
「あれ?聞こえてないのかな?」と思い、「どうぞ〜」ともう一回言ったこともありました。
そして、何も言わずに入って来られまして、レッスンームにも何も言わずに入って来られます。
「こんにちは〜」と声をかけると、無視をする時もあるし、こちらを見ずに「こんにちはー」とボソッとお返事をしてくれる時もありました。
その後にお母さんが「こんにちは〜」とおっしゃいながら入って来られるのでした。
レッスンのご挨拶
多くのピアノレッスンや、その他の習い事でも、始まりの挨拶をされるところが多いかと思います。
私も学生の頃、レッスンの初めには先生に恐縮しながら「よろしくお願いします」と深々と頭を下げ、終わりには「ありがとうございました」とまた深々と頭を下げたものでした。
私のレッスンでは、ワークなどの座学から始めることも多いので、ついつい始まりの挨拶をしないで進めることも多いのですが、終わりの挨拶はしっかりとしてくれる子が多く、お母さんの教育にいつも感謝するばかりです。
小さいうちはまだ敬語が使えなく、「ありがとう」とだけ言う子もいますが、年少さんの小さいお子さんでも「おはようございます!」と大きな声でしっかりと丁寧な挨拶をしながら入ってきてくれる子もいます。
お母さんがおっしゃるには、幼稚園でいつもしている挨拶なので、「こんにちは」ではなく「おはようございます」が定着してしまったとのことでした。
話は変わりますが、芸能界では、朝でも昼でも夜でも「おはようございます」と挨拶されるそうです。これは昔、松竹芸能の社長さんが始められたことらしく、「こんにちは」や「こんばんは」は敬語じゃないから、唯一敬語がある「おはよう」を「おはようございます」と敬語で言い、定着させたとのことでした。
挨拶って、習慣なんですよね。
普段から言っていないと、無意識に出てくることはないと思います。
さて、私が気になるその子ですが、レッスンが終わり、楽譜をまとめて「よくがんばりました。」と言って私が渡すと「ありがとう」と言っていました。
こちらを見ずに歩きながら言いますが、最初は「ありがとう」の気持ちが伝わる言葉でした。
ところが、半年くらい経った頃あたりから、「ありがとっ」と、語尾をあげるようになったのです。
それは例えば、主人が使用人に「セバスチャン、荷物を持ってくれてありがとっ」というような高飛車なイメージです。
ここにも違和感を感じ始めました。
ハラスメント
昨今、あいさつを強要するのはハラスメントにあたるそうです。
しかし私は、人と人とが接するなかで、お互い気持ちよく物事を進めていくには挨拶や礼儀は欠かせないことだと思っています。
そのため、自分の子供が習い事に行く時、先生にお会いしたとき、お別れの時、必ず感謝の言葉とご挨拶をするように教えてきました。
来客には玄関の外までお送りし、「お気をつけて」と言うのですが、気が付けば息子も同じようにお友達にするようになっていました。
ピアノの発表会では、演奏前の礼を何度も練習します。
くにゃくにゃしたり、へらへらしたり、歩きながら頭を下げるのではなく、きちっと。
深すぎない、かっこいい感じに頭を下げます。
そうした練習を息子にもしていたところ、先日、主人の仕事関係で、昔お世話になっていた方のお通夜があり、私も息子もお会いしたことはないのですが、家族で伺った時のこと。最後に祭壇に手を合わせに行き、その横にいらっしゃる「喪主の奥様やご家族に頭をさげてね」と息子に伝えたところ、誰よりも深々と、丁寧に、一人一人に頭を下げている姿を見て、「発表会の時の礼をしている!」と心の中で思いました。。
喪主の奥様も息子に深々と頭を下げられていて💦
亡くなった方は96歳で、大往生ということもあり、ご家族の方も、そんな息子をみて少しお顔がほころんでおりましたので、「よかった」と思いながら胸をなでおろし、帰ってきました。
礼儀正しい挨拶は人の心を和ませるんですね。
ピアノを習うということは、今は私の教室に通ってくれていますが、なんらかの理由により他の教室へ移ることも考えられます。
私に挨拶をしないと言うことは、次に行った教室の先生にもしない可能性があります。
「それではいけない!次の先生に失礼がないように!」と、
あまりにも気になる時は「入ってきたら挨拶しようか」とか、「お礼を言う相手の方を向いてありがとうございましただよ。」
といった指導をします。
特に、他の教室に移る予定の子には念入りに挨拶や、レッスンを受けるマナーの指導をします。
指導をうけたくない子
話が戻りまして、私の気になるその子に挨拶の指導をすると、あからさまにおもしろくないと言う表情になりました。
レッスン中も、お母さんの方をじろりと見て、目配せをすることが増えました。
「注意を受けておもしろくなかったかなぁ。言い方が悪かったかなぁ?」など、私も思い悩むようになりました。
そんな中レッスン中に、「こういう弾き方じゃなく、こんな感じでやってみて」とダメな見本と正しい見本を見せました。
レッスンでは音の違いを理解できるように、よくやっている指導法です。
「そんな弾き方してない!!!!!!」急に興奮して怒り出してしまいました。
その時、やっと気がつきました。
「指導をされたくないんだ」と。
その子はなんでも簡単にできてしまうほどとてもかしこく、器用な女の子でした。
字も上手だし、音符もすぐに読めるようになったし、ピアノを弾くのも得意げでした。
「すごいね、上手だね。」といっぱい褒めてレッスンして来たのです。
でも、やっぱり始めて1年も満たない未熟な子供です。
直すべきところはたくさんあるし、間違えや勘違いも多い。
練習もさっと1回弾くか弾かないかのような、初見で持ってきている感じがありました。
それでもまぁまぁ弾けているので、それで良いと思っていたのでしょう。
それを、レッスンに来るたびに弾けていないところを指摘されたり、弾き方が違うところを指摘されるのです。
ずっと、「おもしろくない」と思って来ていたのでしょう。
その「おもしろくない」の気持ちが「先生を無視する」行為になったのだと悟りました。
「自分はうまい!」と思って来ている子に時々あるのですが、家で1人で弾いていたときは自分が一番!と思っていたのに、教室に通うようになると、「弾き方が違う」「間違いを指摘される」「難しくてすぐにはできない」「他の子は自分よりもっと上手に弾いている」という現実を知り、怒ってしまう子や嫌になっていまう子がいるのです。
習うということ
おうちで楽しく、それなりに上手に弾いているのなら、あえて教室に通わせる必要はないと思っています。
ましてや、お母さんが経験者で、ちょっとくらいの楽譜の読み方なら教えてあげられ、それで本人が満足しているのなら通う必要はないのです。
本人が「習いたい」「もっと上手くなりたい」と思った時に、教室の門を叩く。
それで十分だと私は思います。
クラシックの世界は今も、昔と変わらず礼儀、マナーに厳しい世界です。
コンクールに出るわけではなくても、人前で弾く機会を希望していないとしても、ピアノを習うのであれば、「教えてもらうマナー」「演奏のマナー」「聴くマナー」を身につけていきたい。と考えています。
気になるその子は、その後 私の教室を辞めて、ご自宅から歩いて通える教室へ移られました。
親子間の価値観の相違
「自らが苦海から抜け出したいと念じ、努力しなければ、救われることはない」
これは仏教の教えです。
「苦海」とは文字通り苦しみの海ということです。陸地も見えず、進むべき正しい方向もわからず、ただ泳ぎ続けているだけの苦しみから抜け出したい。そう願って、努力しなければ良い方向には向かわないというお話です。
結局、私はその子に何も教えてあげられませんでしたが、彼女がこの先いろんな人と出会ったり、上手くいかないことや嫌だと思うことにもたくさん出会うと思いますが、無視をしたり、嫌がらせをしたり、嫌な思いをさせることで解決するのではなく、いつか「気配り」や「マナー」、「礼儀」を身につけ、彼女自身が幸せになることを願うばかりです。
私も、自分自信に慢心することなく、生徒やその親御様と認識のずれがないか確認しながら歩んでいきたいと思った出会いでした。
「ピアノ教室に通ってみる?」と子供に提案する前に今一度、「習う」とはどういうことなのか、本当にプロに習いたいのか、親子間で認識のずれがないか確認してみていただけたら幸いです。


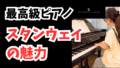
コメント