ピアノには「お家練習」がつきもの
華々しい演奏の影には、地道な練習が9割と言って良いほどピアノ習得には「練習」が必要です。
そんなお家練習ですが、小さなお子さんが自発的に練習を好んでするかというと、ほぼ確実にそうではありません。
もし、小さな頃から大人の手を借りずに練習を率先してやり、すいすいと楽譜を読み、楽しく演奏しているのなら、その子はとてもピアノの素質があり、将来 音大や演奏家を目指すことも可能なほどの才能を持っていると思います。
でも、ピアノってとても難しいので、たいていのお子さんはとっても苦労しながらやっています。
もちろん、大人の手を借りないと続けていけません。
大人の手を借りられなかったり、楽しくない練習を続けている子はもれなく挫折していきます。
それでは、どうしたらピアノを続け、将来ピアノを自由に奏でられる子になれるのでしょうか。
今日は、そんなお話をしていきたいと思います。
子供がピアノを習い始めたら、絶対にやってもらいたいこと
それは、「頑張りを認め、よく褒める」ということ。
突然ですが、お母さんやお父さんは、子どもの頃ピアノを習っていた経験はありますか?
「経験ありません。」という方もいらっしゃいますが、「経験あります」という方が半数以上のように感じます。
そのほとんどの方が途中で辞めているのです。
では、なぜ辞めることになったのか?
それは、「弾けない」「読めない」「練習が嫌い」ではなかったでしょうか?
稀に、「高校まで続けました」という方もいらっしゃいますが、「親に強制されていたから、早く辞めたかった」「今は全く弾けない」というお話はよく聞きます。
ピアノに限らず、勉強おそうですが、練習が必要なものは、勉子供は親に強制されるとやりたくなくなります。
親がピアノに興味を持たず、放置される子なんかも早々に辞めていきます。
それくらい、お母さん、お父さんの「認めて褒める」の影響力ってすごいのです。
なので、最初は下手でも間違っていても良いのです。
「頑張っててえらいね。」「上手になったね、もう1回聞かせて!」「随分うまくなったね。」
とにかく、誉めてあげてください。
そして、最初は週3回からでも良いので、少しずつ毎日練習できるように、練習する声がけをしてあげてください。
子供って、時間の概念があまりないので、予定を立てることが苦手です。
なので、「おうちに帰ったらすぐ弾く」「学校に行く前に弾く」「寝る前に弾く」「夜ご飯のあとに弾く」など、生活のルーティンにくっつけて、弾く時間をお子さんと一緒に決めていきましょう。
生活が変わる覚悟
生活のなかに、今までやってこなかった「ピアノを弾く」ということを取り入れるということは、少なからず生活が変わるということ。
お母さんやお父さんは、ピアノを弾く時間の声がけをして、うんと認めて誉めてあげること。
これを、毎日続ける覚悟を持っていただきたい。
時には気分がのらなくて「今日はやりたくない」と言う日もあるでしょう。
でも、気分によって「弾く・弾かない」を決めていては、練習が定着しないのです。
気分が乗らなくても、「1回だけ弾く」「指の練習だけやる」など、ほんの少しでもよいので弾かせてください。
「気分がのらないんだね、そしたら1曲だけにしておこう」と優しく声をかけてあげてください。
「お母さんが一緒にいるから」と言って、隣に座って見守ってあげると喜んでやると思います。
絶対にやってはいけないこと
それは、怒ってやらせようとすること。
怒ってやらせて、イヤイヤやっても、何にも身にならないのです。
レッスンでは、音符ワークをやるのですが、音符ひとつ覚えられない子がいました。
何回やっても、何ヶ月たっても、1年経っても、ひとつも覚えられないのです。
「はぁ〜」とため息をついたり、やりたくない態度全開の子だったら「やりたくないんだな。」とわかります。でも、態度に合わらさず、声にも出さず、ルーティンのようにワークに向かうので気がつくのが遅れました。
「やりたくない」と思いながら「早く時間が過ぎれ」と思いながらイヤイヤ、沈黙でやっていたのです。
「やりたくない」子には、「やりたくないのならやらないよ。」と伝えます。
脅しではなく、本当にやりません。
音符を読む練習は、ワークだけではありません。向き不向きももちろんあります。やりたくないのにそのまま続けても、半年たっても1年経っても一つも覚えないのです。
この時に、やりかたを変える場合もありますし、「やらない」と私が言うと「いや、やる!」と言って謎のやる気を発動させる子もいます。
このやりとりの後は、どの子もみるみる音符が読めるようになっていきます。
やる気の「ある・なし」はとっても重要なのです。
だから、絶対に怒って恐怖を植え付けてやらせるのはやめてください。
それに、本来音楽って楽しむものです。
怒られて、楽しくない気持ちでやったって、そこに喜びはひとつもないのです。
お母さんは先生ではありません。
時々、お母さんが経験者なだけに、間違いを指摘したり、譜読みを手伝ったりしているうちに親子仲が険悪になってしまっているケースを見かけます。
親が先生ではないのです。
楽譜の読み方、ペダルの踏み方、手首の使い方、体の使い方。
どれをとっても専門に学んできた先生とは比べものにならない技術力ですし、経験値も全く違います。
「お母さんがこういった」「お母さんが教えてくれた」と言って、間違った弾き方を覚えてくる子ほど、レッスンしづらいものはありません。
そういう場合は、お母さんを否定することはできませんので、正しく修正したり、いちから教えることもやりません。やったところで、子供が反発するだけなのです。
その後、子供が成長するとお母さん先生は成り立たなくなってきます。
お母さんに口出しされるのが嫌になるのです。
そうなった時、しっかり教室で基礎を学べなかった代償は大きいです。
1人では上手くできなくて、挫折してしまう原因にもなりうるのです。
目標を持って、親子で共有すること
ピアノはいつまで続けると弾けるようになるのか?
幼児期や小学1〜2年生から始める子が多いと思いますが、体を上手に使い、楽譜も1人で読めるようになるには、中学卒業くらいまで続けると良いのではないかと思います。
手指は、子供の頃に比べ大きくなり、大人の大きさに近づきます。
それに伴い、動きもとても良くなってきます。
楽譜読みに至っては、習えばすぐに読めるようになるのかというと、たいていの子はそうではありません。
1年1年上達しながら、少しずつ完璧な譜読みを目指していくのです。
もちろん、個人差はありますし、家での練習量、正しい練習をしているかによっても上達スピードは違います。
それを理解した上で、いつまで続けるのか、今の目標は何なのか、お子さんとよく話しあうと良いと思います。
コンクールを目指すのなら、1日1時間以上の練習は必要ですが、将来ピアノを楽しむスキルを身につけたいのであれば、15分〜30分でも良いので、毎日続けることが必要です。
上手くなるには
どんな子でも、練習さえすればコンクールを目指せますが、それには家族の協力が必要です。
いくらレッスンでテクニックを教えても、子供は忘れてしまいますので、それを記憶して実践して、練習によって定着させることが必要なのです。
それは子供だけではできないので、お母さんがレッスンを録画するとか、練習時間を増やす声がけをして、時間の管理をするとか、色んな演奏会に行って、一流の音楽に触れるとか、お子さんのマネージャーだと思ってフォローすることが大切です。
しかし、覚えておいてもらいたいのは、家族のフォローと練習量でコンクール予選までは勝ち取ることが出来ても、その先の本選入賞となると、練習量だけでは勝ち取ることができないことも多いのです。
やればやっただけ身についていくお勉強と違うのが、このピアノの難しいところであり、面白いところでもあります。
審査員も人間ですから、好みがあったり、考え方の違いがあったり、重要視している点がその方によって違ったり、思いの外うまい子が多かったり、いろんなことがからみあって、運もあっての入賞なのです。
どんなに有名なピアニストでも、完璧な演奏をしたからって、みんな毎回1位をとれるわけではないのです。
コンクール入賞については、演奏を楽しんで、頑張れたことをうんと認め、誉め、勝ち負けにこだわらないのがポイントです。
運がよければご褒美(トロフィー)をもらえると思っていれば、入賞できなかったときのショックも少し和らぐかな、と思います。
入賞できなくても、ご褒美を買ってあげるというのも、とってもモチベーションが上がる方法だと思います。
子供を1人にしない
「練習しなさい」と言うだけで放置するのが、一番かわいそうだと私は思います。
お母さんが全くピアノに興味がなく、ピアノも買ってもらえず、2年たってやっと買ってもらえたと思ったら「うるさいからヘッドフォン使って弾いて」と言われる始末。
これでは楽しくないのです。
聴いてもらって、「すごいね、うまいね。」と言ってもらえるから楽しく続けられるのです。
「レッスンさえ楽しければ続けられるかな」と思い、その子に寄り添い、たくさんお話しをし、少しでも興味を持った曲はすぐに購入して弾かせ、頑張りましたが、ある日「もう弾きたくない」と泣きながら言い、辞めていった子がいました。
聞けば、狭い物置部屋にピアノが置かれ、椅子を引くこともできない状態で、音がもれないように小さい音で、ヘッドフォンで弾いていたそうです。毎日は弾くことができないので(うるさいと言われるから)、もちろん練習も定着せず、それでも3年続けましたが辞めていきました。
子供の「やりたい!」に答えてあげたのなら、全力で応援してあげてもらいたい。
小さなうちは、「練習しよう!」と誘って、一緒に練習するとか、そばで見守ってあげると良いと思います。
息子は小学4年生ですが、「聴いててね」と毎回言います。
私が指導しているのですが、そばにいるとうるさく口出ししてしまうので、少し離れたところで聞くようにしています。
週に1回は「レッスン」のため、うんと口出ししますが、日々の練習で音間違えがあっても指摘しません。
何度か弾いているうちに自分で「あれ?へんだなー?あれ?こうかー!」と言う具合に、気がつけるようになってきます。
これも学びなのです。
子供が小さいうちは、できなくて当たり前なんです。
私も、親がノータッチだったので、1人で練習していましたが、毎回先生に厳しく怒られていたので、自分では「弾けてる」と思っていましたが、全然できていなかったのだと思います。
でも、その経験があるからこそ、今レッスンができているのだと思います。
子供達が苦戦し、壁にぶち当たるようなことは、私も同じように経験してきたことであり、親の手を借りずに1人で乗り越えてきたことで自身に繋げ、今の私があると思っています。
子どもには子どもの人生の学びがある
私の場合、親がうるさく口出ししなかったから、この年まで楽しく続けられたのだと思っています。
子供には子供の人生があり、学びがあります。
親の希望を押し付けて強制することくらい、お互い幸せにならないものはないと思ってます。
間違えたって、上手くできなくたって、それも学びなのです。
私の教室では、「ピアノを弾きたい!」とお子さん本人が希望していることを入会条件としています。
お母さんが弾かせたくて、説得したところで、本人にやる気が芽生えないと早々に親子共々挫折していってしまいます。
そのごたごたに振り回されるピアノ講師ほど最悪なものはないというのが、ピアノ講師の本音ではないでしょうか。
ピアノが弾けるようになってもらいたい!
と思うのなら、お母さんがピアノを楽しむ。
ピアノ経験がないのなら、リトミックに通わせる。
私の教室のリトミックでは、ピアノに繋げる音楽遊びで、基礎を学び、グランドピアノの生演奏を聴いて「私も弾きたい!」の興味を引き出します。
まとめ
いかがでしたか。
「お母さんにピアノ経験がないと、子供はピアノが弾けるようにならない?」と
よく質問を受けますが、そうではないことがお分かりいただけたでしょうか。
ピアノを習うのなら、楽器は安い買い物ではないのですかから、家族全員で応援してあげてくださいね。
こちらも参考にしてください☺️↓


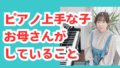
コメント